自己肯定感とは
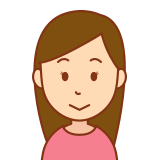
最近耳にする「自己肯定感」ってどういう意味なのかしら?

それでは、わかりやすくご説明します!
単に自分に自信があるとか、ないとか、そういう事ではなく、『私には存在価値がある』とか『大切な人間だ』『必要な存在だ』とか、『生きていていいんだ』『私は私でいいんだ』といった気持ちのことです。

つまり、良い自分も悪い自分も全部まとめて、私は私で存在価値があると思える気持ちのことです。
実はこの「自己肯定感」こそが、こどもの心を成長させる土台となるものなんです。自己肯定感がしっかりと築かれている子は、しつや、生活習慣、さらには勉強がしっかりと身についていくのです。逆にいうと、しつけや生活習慣、勉強に何らかの問題が生じている場合、根本の原因は、自己肯定感がしっかり育まれていない事なのかもしれません。
子供の自己肯定感が低いとどうなる?
自己肯定感が低い子に、しつけや勉強を教えようとしてもなかなか身につきません。逆に言えばいうほど「自分は出来ない、だめなやつだ」と自己肯定感を更に傷つけてしまいます。ひきこもり、拒食症・過食症、少年犯罪、自殺未遂など、さまざまな子供の心配な症状を引き起こす要因は、自己肯定感の低さからきている事があげられます。
「自分は役に立たない人間だ」と思っている子が、勉強に熱心に取り組んだり、社会のルールを積極的に守ったりできるでしょうか?
「生きている価値がない」と思っている子が、人生を前向きに生きていけるでしょうか?

人生の幸・不幸は学力のあるなしでもなく、能力のあるなしでもなく、自己肯定感のあるなしで決まります!
自己肯定感が低くなりつつあるサインとは?
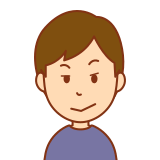
どうせ、ぼくなんか・・・
この「どうせ無理」「どうせ私なんか・・・」という言葉が出てきたら、要注意です。これは自己肯定感が低くなってきた時に、たいていの子どもが必ずといっていいほど口にする言葉です。そういう子は、すでに自信を失いかけているので、叱らないようにしましょう。
こどもの自己肯定感の育て方&育て直し方

自己固定感を育むのは0〜3歳までが理想です。しかし、安心してください。いくつになっても育て直しはじゅうぶん出来ます。気付いた時から自己肯定感を育て直しましょう。ではどのように自己肯定感を育てれば良いのでしょうか?

いくつか具体例をご紹介します
良いところも悪いところも受け入れる
子供のいいところを褒める事は、どの親でもよくやる事だと思います。では、悪いところを受け入れるという事はどういうことでしょうか?それは、子供が悪い事をしても注意をしない、という事ではありません。例えば、子どもがとんでもないような言葉を使って兄弟喧嘩してたとします。

こらーーーーー!なんて言葉使うのーーー!!!※%$&’%#”$&’((#”$←怒怒怒

がーん。お母さんがあんなに怒ってる・・・もう見捨てられるかも・・・家を追い出されるかも・・・
・・・数時間後

ごはんよー!みんなで食べようー!

あ、いつものお母さんだ。よかった、こんな自分でもお母さんはちゃんと受け入れてくれるんだ。よかった!(安心)
これが、悪いところも受け入れてもらえるという感覚です。このいいところも悪いところもひっくるめて愛してもらえて育つのが、自己肯定感です。
スキンシップ
こどもは、抱っこされる事で「自分は大事にされている」と感じます。抱っこやハグ、手を握るなどは「自分は大切にされて価値のある人間なんだ」という自己肯定感を育てます。

「抱き癖がつくので抱っこはダメ」というのは間違えだったんです!
話をきく
こどもの話をしかっり「うんうん」と聞いてあげることで、こどもは「自分はちゃんと話を聞く価値のある子なんだ」と思います。この時に聞くコツは、相手の言ったことを繰り返してあげることです。

今日こんなことがあって・・・イライラしたんだよね!

そっかー。そういうことがあって、イライラしたんだね
これで、こどもは「わかってもらえた!」という気持ちになります。
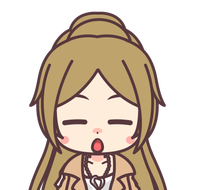
じゃぁ、こうすればイライラしなかったんじゃないの?
なんてことをいいがちですが・・・繰り返すことに徹しましょう!
ここまで書いた事は、ほんの一例ですが、ぜひ参考にしてくださいね。
実は大人も自己肯定感が低い?
こどもの自己肯定感を育むことも大事ですが、じつは大人も自己肯定感が低いまま成長してきた、という方も少なくありません。何か問題にぶつかった時、ぜひ自分の自己肯定感についても考えてみてほしいと思います。
さいごに
子育てをしていると、さまざまな悩みが出てくると思います。そんな時に「私の育て方のせいで」「私が悪かったんだ」そんなふうに思い込んでしまわないでください。子供というのは自己中心的で失敗をします。言うこともなかなかききません。でもそれは、子供が成長していく上で、必要なプロセスの一つなのです。成長とともに解決することは多々あります。
ですから、私たち育てる側もあまり真面目にならずに、「この子はこの子なりに精一杯やっているし、私も一生懸命やっている」と現実を認めましょう。育てる側として、自分はじゅうぶん頑張っていると認めてあげてください。

少なくとも、子育てについての記事を読んでいるあなたですから、じゅうぶんに子供のことを考えている素晴らしい方だと思いますよ
また世間が、子どもや子育てする親を暖かく見守ってくれる世の中になればいいなと思います。

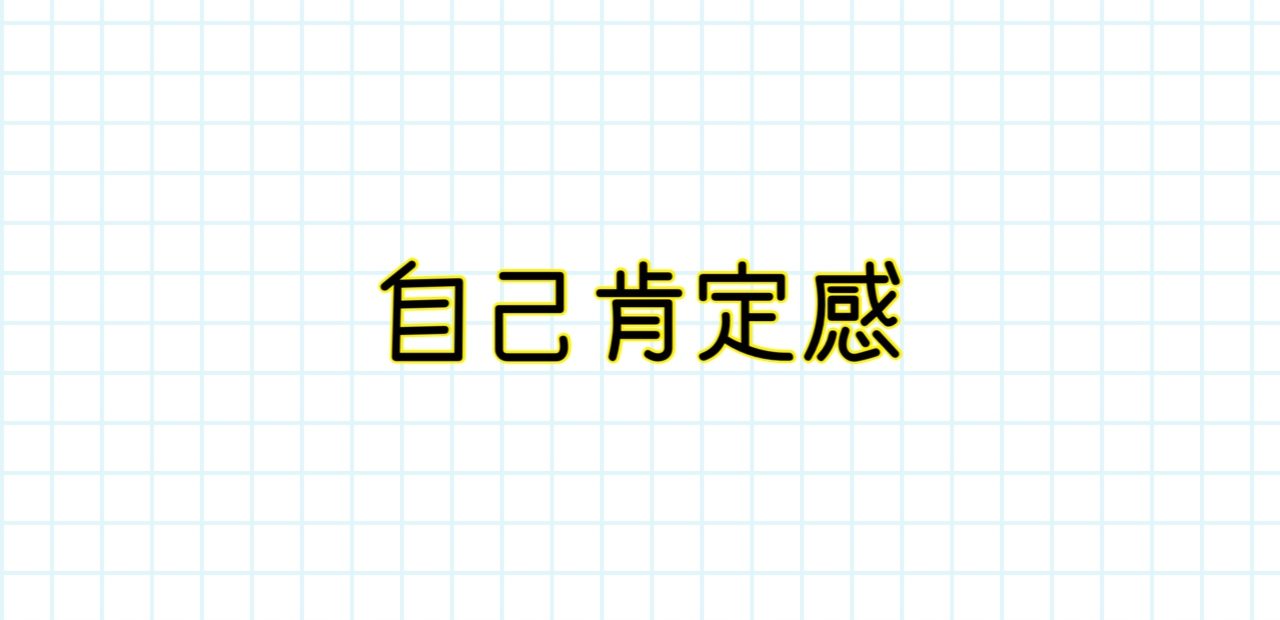
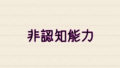
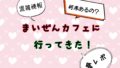
コメント